ウェルネス旅行で拡大する「食体験」の重要性
- VIVIFY Team
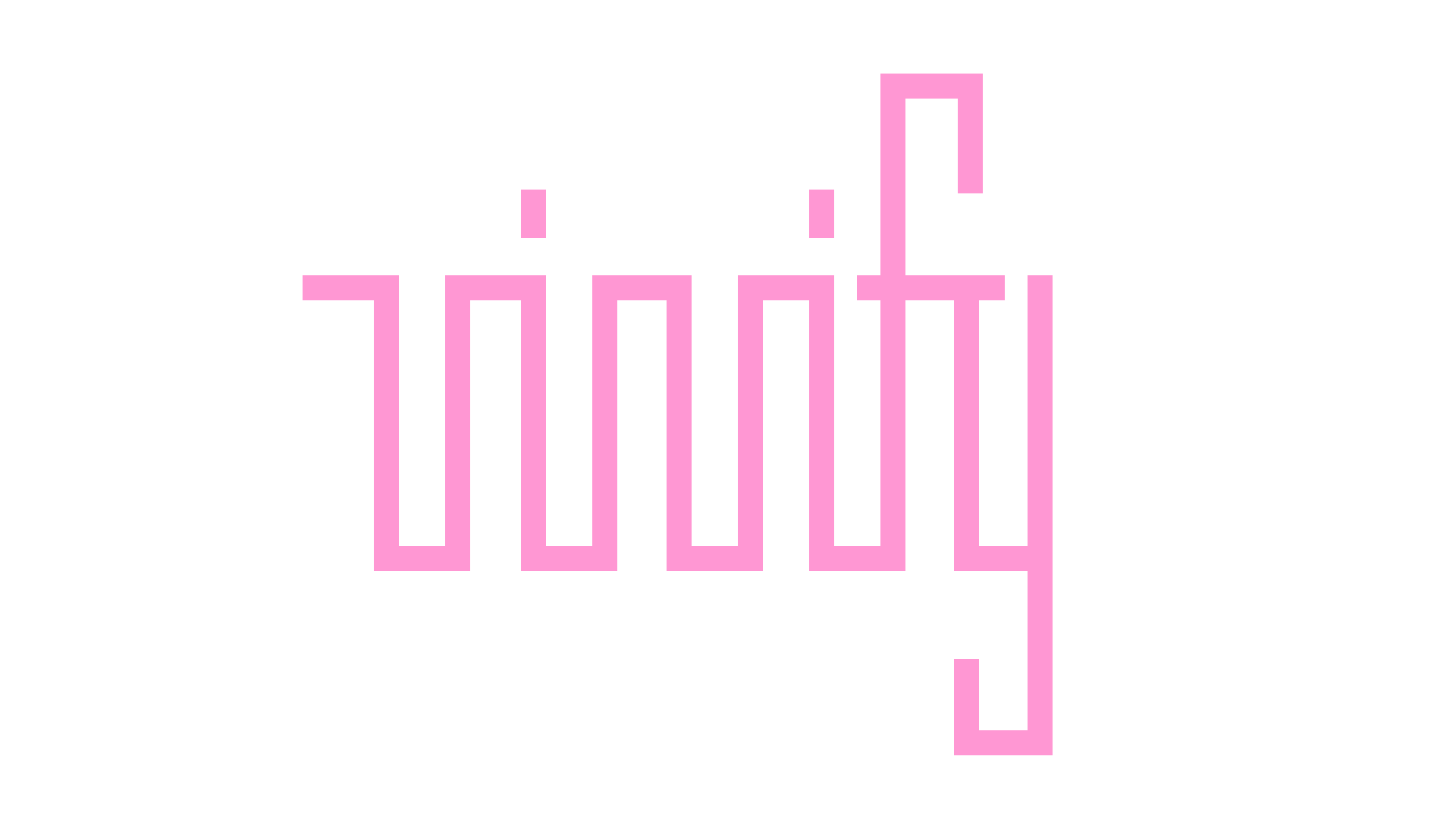
- 2025年3月3日
- 読了時間: 7分

世界的にウェルネスツーリズムの人気が高まる中、その旅先での「食」の重要性が改めて見直されています。スパやヨガといった定番のウェルネス要素に加え、「何を食べるか」が旅の質、そして心身の健康を大きく左右するという考えが広まっています。
実際、American Express の調査では、旅行者の81%が「旅行中に最も楽しみなのは地元の食文化を味わうこと」と答えており、また 別の海外の調査でも67%の旅行者が旅先で健康的な飲食オプションが提供されることを重視すると報告されています。総じて、ウェルネス旅行においても食体験は単なる栄養補給以上に、心身の健康と旅の満足度を左右する中心的な要素となりつつあります。
食を含むウェルネストラベル需要の拡大
ウェルネス旅行市場は年々成長を続け、パンデミック後の反動もあって急速に回復しています。Global Wellness Instituteによれば2023年のウェルネス旅行支出額は 8,300 億ドル規模に達し、旅行者は「旅先でも日頃の健康的なライフスタイルを維持・実践したい」と考えるようになっています。こうした潮流を受け、旅行業界もウェルネスと食を組み合わせたサービス開発を加速させています。
また、ある国際調査では、2024 年に体験内容を拡充した事業者のうち 39% が新たに現地の料理体験を提供し始めたとされ、旅行プランに料理や食育プログラムを組み込む動きが顕著です(同調査では全体の8%が「料理体験を新規追加した」)。また、 American Express Travel の 2023年トレンドレポートでも、今年の旅行キーワードの一つに「食」が挙げられており、「ウェルネス」と並んで今後の旅行コンセプトを左右する重要テーマとなっています。
つまり、ウェルネス旅行における食体験の需要はデータから見ても明らかに拡大傾向にあるのです。
3大キーワード:脳腸相関・マインドフルネス・サステナビリティ
食体験が注目される背景にはいくつかの要因があります。第一に、近年の研究で明らかになってきた「脳腸相関」(gut-brain axis ガットブレインアクシス)への関心です。
腸内環境とメンタルヘルスの密接なつながりが知られるようになり、心身の調子を整えるには「何を食べるか」が極めて重要だと科学的に証明されました。日本は、漢方やプロバイオティクスが広く普及していることから、脳腸相関の潜在的な理解は心の病を処方薬で優先的に対処してきた西洋と比較して強いともいえます。
保育園や小学校に管理栄養士を配属させるなど、食事から人を育てる日本の文化が今になっては欧米を中心に注目されています。日本食で多く含まれているプロバイオティクス豊富な発酵食品や食物繊維が豊かな穀物、抗炎症作用のある食材などはウェルネス志向のメニューとして採用されています。

可処分所得が高いことが特徴のウェルネス旅行者は、油が多く腸への負担が大きいフレンチやイタリアン、鉄板焼きなどの定番ジャンルよりも、腸活を考えた伝統料理を取り入れたメニューを求めていることを、今後のホテル・商業施設・リゾート開発において意識する必要が高まってきています。
そしてもう一つの忘れてはいけないキーワードは、マインドフルネス。マインドフルネス(心の充足)の潮流も食への注目を後押ししています。食事そのものを瞑想やセルフケアの機会と捉え、ゆっくり味わう「マインドフル・イーティング」がウェルネスプログラムに取り入れられています。

例えばシンガポールのウェスティンでは、敢えて会話を控え、静寂の中で味わう「サイレント(黙食)朝食」という試みを導入しており、食事を通じて内省や心の安定を促す場を提供しています。スマホやテレビのながら食事が増えてきている時代だからこそ、このように五感に集中しながら食べる体験は、ストレス軽減や満足度向上につながると注目されています。
もちろん、ながら食事をしないことが身体にいいということは科学的にも証明されています。食事を見たり香ったりすることで、消化が促されるため、他のことをやりながら食べると腸に負担をかけてしまうことも。
そして、3つ目のキーワードは、やはりお馴染みの「サステナビリティ(持続可能性)」。ウェルネスと環境意識は切り離せない関係にあり、「未来の食とダイニング体験はウェルネスとサステナビリティが形作る」とも提唱されています。
具体的には、有機農法や再生農業(リジェネラティブ)による食材調達、植物性タンパク質を主役に据えたプラントベース料理、フードロスを出さないクローズドループ(循環型)の食材活用がポイント。それに、旅先で地産地消の食を味わうことは環境負荷低減に寄与するだけでなく、その土地の文化やコミュニティとのつながりを実感できる体験でもあります。

こうした理由から、「健康に良い食事=地球にも地域社会にも優しい」食事であるという認識が広がっており、ウェルネス旅行において持続可能な食体験への期待が高まっているのです。
具体的なウェルネス×食の体験事例
では、実際にどのような食のウェルネス体験が提供されているのでしょうか。先進的なホテルやリゾートでは、以下のような取り組みが行われています。
ファーム・トゥ・テーブル(Farm-to-Table):
宿泊客自ら畑や農場を訪れて収穫を行い、その新鮮な食材で料理を楽しむ体験です。地元農家と連携したり、自前のオーガニックガーデンを持つ施設も増えています。実際、滞在中に敷地内農園で採れた季節野菜を使った料理教室や、地元農場へのツアーを組むリゾートもあります。
インドのあるリトリート施設では、村の女性たちが薪火でじっくり調理した伝統料理をゲストが味わう夕食イベントが好評で、その土地ならではの食文化とヘルシーさを両立した例として挙げられます。
プラントベース&オーガニック料理:
肉類を控え野菜や豆類、穀物中心で栄養バランスに優れた食事を提供する試みです。ヴィーガンやベジタリアンメニューを全面に打ち出すウェルネスリゾートもあり、有機農園で採れた食材をふんだんに使った「畑のごちそう」を提供しています。
ある米国のウェルネス牧場では、一週間の滞在中にプラントベース中心の食事を提供した結果、参加者のウエスト周りが平均 2.7cm 減少し血圧も有意に低下するといった健康改善効果が報告されました。美味しさと健康増進を両立する植物性中心の料理は、今やウェルネス旅行の定番となりつつあります。
アーユルヴェーダ&栄養コンサルテーション:
インド発祥の伝統医療アーユルヴェーダの知恵を取り入れ、体質(ドーシャ)に合わせた食事を提案するプログラムです。
アーユルヴェーダの専門家や栄養士が常駐し、ゲスト一人ひとりの体調や目的に応じた食事メニューを診断・提供するホテルも増えています。例えばチェックイン時にカウンセリングを行い、「胃腸を整えたい」「免疫力を高めたい」などニーズに即したハーブやスパイスを用いた特別メニューを用意してくれる施設もあります。食養生の観点から旅行者のウェルネス目標をサポートする取り組みです。
このように、ウェルネスに食をどう取り入れべきかの正解はないのですが、取り入れることで差別化を図ることができるのは間違いないです。食を起点としたウェルネスが豊富な日本だからこそ提供できる事業展開も多いでしょう。
おわりに:ウェルネス×食体験を取り入れた施設づくりに向けて
「食」を重視したウェルネス旅行の潮流は、施設開発やブランド戦略にも新たな機会をもたらしています。ヘルシーで持続可能、かつ地域性豊かな食体験を提供できる施設は、今後ますます差別化された存在として支持を集めるでしょう。
このような海外のトレンドを早い段階で取り入れることで施設の付加価値を高めることも、富裕層など可処分所得の高いインバウンドの集客を行うことも可能です。
VIVIFYが最新トレンドと実践事例を踏まえ、貴施設ならではのコンセプト作りをサポートします。ウェルネス×食の体験づくりについて、ぜひお気軽にご相談ください。



コメント